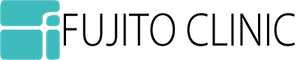思春期の子どもの心のSOS、見逃さないで。社会全体で支える新たな取り組みとは?
「最近、うちの子、口数が減って部屋にこもりがち…これって反抗期?」
思春期のお子さんを持つ保護者の方なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるかもしれません。その態度の変化は、単なる「難しい年頃」だからではなく、言葉にできない「心のSOS」のサインかもしれません。
『藤東クリニック インサイト』の動画シリーズ「女性のための、こころの保健室」第2回では、最新の公的データ『令和6年版厚生労働白書』などを基に、「思春期のお子さんの心の健康」について詳しく解説しています。今回はその内容をダイジェストでご紹介します。
思春期の心の不調は「特別なこと」ではない
かつては「気合が足りない」「気の持ちよう」などと言われがちだった心の問題。しかし、厚生労働白書によると、10代から20代は生涯の中でも特にうつ病や不安障害といった精神的な不調をきたしやすい時期であることが示されています。
この変化を受け、社会の認識も大きく変わりました。2018年度からは、高校の保健体育の教科書に「精神疾患の予防と回復」という項目が正式に加わっています。今の高校生は、心の不調が誰にでも起こりうること、そして早期に専門家へ相談することの大切さを学校で学んでいるのです。
深刻化する「いじめ」に、学校の外からも支援の手
お子さんの心に大きな影響を与える問題の一つが「いじめ」です。2022年度には、いじめの中でも特に心身に大きな被害が生じるなどの「重大事態」と認定された件数が、全国で923件にものぼりました。
この深刻な状況に対し、国は学校現場だけの努力に頼るのではなく、新たな対策に乗り出しています。文部科学省だけでなく「こども家庭庁」が中心となり、自治体の首長(市長や知事)がリーダーシップを取って、第三者の専門家を交えたいじめ対策の体制づくりを進めています。学校内だけでは解決が難しい問題も、地域全体で子どもと保護者を支え、いじめの長期化や重大化を防ぐことを目指しているのです。
子どもの”いのちの危機”を防ぐ、社会のセーフティネット
最も避けなければならない事態は、悩みの末に子どもが自ら命を絶ってしまうことです。この喫緊の課題に対し、国は2023年6月に「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめました。
このプランに基づき、各都道府県・政令指定都市には、精神科医や臨床心理士などの専門家で構成されるチームが設置されています。自殺のリスクが高いなど、市町村や学校だけでは対応が困難なケースにおいて、この専門家チームが直接的な支援や助言を行う体制が強化されているのです。国が費用を全額補助するなど、社会全体で子どもたちの命を守り抜くという強い意志が示されています。
家庭でできることと、頼れる相談窓口
社会の仕組みが整っても、やはり一番身近な大人の役割は重要です。
- お子さんの小さな変化に気づき、対話を続ける
「最近元気ないけど、何かあった?」と優しく声をかけるだけでも構いません。 - 気持ちを否定せず、まずは受け止める
「そうなんだね」と、まずはお子さんの気持ちに寄り添うことが大切です。
そして、ご家庭だけで抱えきれないと感じたら、決して一人で悩まないでください。今、相談できる窓口は以前よりずっと充実しています。
- 保健室(養護教諭)やスクールカウンセラー:心と体の両面から相談できる、学校内の身近な窓口です。
- こども家庭センター:2024年4月から全国で展開が始まった新しい相談拠点。妊娠期から子育て期まで、切れ目のない支援を提供します。
私たち藤東クリニックも、産婦人科として思春期から始まる女性の心と体の変化に寄り添っています。
思春期のお子さんの悩みは、ご家庭だけで抱える必要はありません。社会には幾重もの支援の網があることを、どうか知っておいてください。