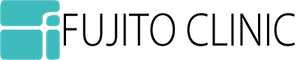【人間関係に疲れたあなたへ】データで見る「孤独」との向き合い方と、こころを支える“人とのつながり”
「なんだか、ふと寂しくなる…」「人間関係に少し疲れてしまった…」
忙しい毎日の中で、そんな風に感じることはありませんか?
私たちの心の健康は、日々の人間関係に大きく影響されます。特に、進学や就職、ライフステージの変化などで一人暮らしをされている方の中には、孤独感を抱えやすい方もいらっしゃるかもしれません。
YouTubeチャンネル『藤東クリニック インサイト』では、最新の公的データである『令和6年版厚生労働白書』を基に、私たちの「こころの健康」と「人とのつながり」について、分かりやすく解説しています。
この記事では、その動画コンテンツ「【人間関係に疲れたあなたへ】「孤独」は悪いこと? こころの健康を守る“人とのつながり”」の内容をダイジェストでご紹介します。
心の支えになる存在、第1位は「同居の家族」
厚生労働省の調査によると、「こころの健康に良い影響を与えてくれる存在は誰か?」という問いに対し、最も多かった答えは「同居の家族」でした。「よい影響を与えている」「どちらかといえばよい影響を与えている」を合わせると、実に67.3%にものぼります。
次いで「別居の家族」(59.6%)、「学校や職場以外の趣味・社会活動等における友人・知人」(47.5%)と続いており、様々な人間関係が私たちの心を支えてくれていることが分かります。
特に「同居の家族」の存在は年代が上がるにつれてより大きくなり、20代では56.7%ですが、70代以上では78.6%にまで上昇します。ライフステージの変化と共に、家族がより大きな心の拠り所になっていく傾向が見られます。
一人暮らしは孤独を感じやすい?データが示す実態
一方で、このデータを見て「一人暮らしだから、少し寂しいな」と感じた方もいるかもしれません。
実際に、同居している家族がいる方と、一人暮らし(単身者)の方とでは、孤独を感じる頻度に明確な違いがあることがデータで示されています。
-
孤独を「しばしばある・常にある」と感じる人の割合
- 同居人がいる人:7.5%
- 単身者:17.5%
-
孤独を「決してない・ほとんどない」と感じる人の割合
- 同居人がいる人:57.9%
- 単身者:38.6%
データを見ると、一人暮らしの方は孤独を感じる頻度が高いだけでなく、孤独をほとんど感じずに生活している人の割合も、同居家族がいる方に比べて低いことが分かります。
しかし、最も大切なメッセージは「孤独を感じること自体は、決して特別なことでも悪いことでもない」ということです。寂しさや孤立感が辛いと感じる時は、あなたの心が休息や誰かとのつながりを求めている大切なサインなのかもしれません。
鍵は「第2、第3のつながり」。単身者の心を支える人間関係とは?
では、同居家族という大きな支えがない単身者の方々は、どのような人間関係を心の拠り所としているのでしょうか。ここに、非常に興味深いデータがあります。
「学校や職場以外の趣味・社会活動等における友人・知人」が良い影響を与えていると答えた人の割合は、同居者がいる人では45.8%だったのに対し、単身者では55.6%と、10ポイント近く高い数値を示しています。
さらに、「過去属していた学校・職場の友人・同僚」についても、単身者の方が高い傾向にあります。
このデータから見えてくるのは、単身者の方々が、趣味の世界や、かつて築いた人間関係といった、より個人的で私的なつながりを積極的に育み、それを心の支えにしている姿です。
心の健康を支える「つながり」は、必ずしも血縁や今いる組織の中だけにあるわけではありません。
- 自分が「心地よい」と感じられるコミュニティに身を置くこと
- 利害関係のない昔の友人と会い、学生時代に戻ったような時間を過ごすこと
こうした“第2、第3のつながり”が、私たちの心を豊かにし、孤独感を和らげる大きな力になってくれる可能性を、データは示唆しているのです。
まとめ:多様な「つながり」を大切に。一人で抱え込まないで。
多くの方にとって家族が大きな心の支えであることは間違いありません。しかし、たとえ今一人で頑張っている方でも、決して孤立しているわけではないのです。あなたが心地よいと感じる友人や仲間とのつながりは、あなたの心を支える大きな力になり得ます。
どうか、その様々な形の「つながり」を大切に育んでいってください。
そして、もし人間関係に疲れてしまったり、どうしようもない孤独感に苛まれたりした時は、決して一人で抱え込まないでください。私たち産婦人科医は、女性のライフステージにおける様々な体の変化と、それに伴う心の変化に寄り添う専門家です。
藤東クリニックは、いつでもあなたのための場所です。どうぞ、お気軽にご相談ください。