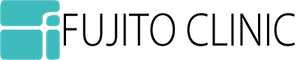妊娠・出産・子育ての不安を安心に。知っておきたい『はじめの100か月の育ちビジョン』と『こども家庭センター』
女性の健康に関する信頼できる情報を分かりやすく発信するYouTubeチャンネル『藤東クリニック インサイト』。この度、心の健康に焦点を当てた新シリーズ『女性のための、こころの保健室』がスタートしました。
記念すべき第1回目のテーマは、多くの女性が経験する「妊娠・出産・子育て期」の心の健康について。最新の公的データ『令和6年版厚生労働白書』を交えながら、この時期に抱えがちな不安を安心に変えるための、心強い仕組みが紹介されています。
「自分は大丈夫?」妊娠・子育て期に押し寄せる、見えない不安
「母親になる喜びと同時に、『自分は大丈夫だろうか』『社会で孤立したらどうしよう』という、これまで感じたことのない不安が押し寄せてきて…」。
動画では、妊娠中の女性が、児童虐待で亡くなる子どもの約半数が0歳から2歳というデータに触れ、ショックと共に自身の不安を吐露する場面から始まります。 このような不安は、決して一人だけの悩みではありません。だからこそ今、国を挙げて、妊娠期から子育てまでを社会全体で支える仕組みが強化されています。
子どもの一生の土台を作る『はじめの100か月の育ちビジョン』
その心強いビジョンが、2023年12月に国が策定した『はじめの100か月の育ちビジョン』です。
これは、母親のお腹の中にいる妊娠期から、子どもが小学校1年生になるくらいまでの約3000日間を指す言葉です。 この「はじめの100か月」は、子どもの生涯にわたる心と体の健康、すなわち「ウェルビーイング」の土台が作られる、非常に重要な時期だと考えられています。
この大切な時期に、特に重要になるのが以下の2つです。
- アタッチメント(愛着)の形成
赤ちゃんが不安な時に、保護者など身近な大人が優しく寄り添うことで生まれる「安心感」や「絆」のこと。これが、その子の自己肯定感や、他人を信頼する力の基礎となります。 - 豊かな遊びと体験
様々なものを見たり、触れたり、友達と関わったりする中で、脳や心が大きく成長していきます。
孤立させない社会へ。相談窓口の新たな拠点『こども家庭センター』
しかし、子育て中の家庭が孤立してしまうという課題も指摘されています。特に、保育園や幼稚園に通っていない子どもは、家庭外の人と関わる機会が少なくなりがちです。
こうした背景から、子育てに不安を抱える家庭を孤立させないよう、妊娠期から切れ目なく支援する中心的な役割を担うのが、2024年4月から全国の市区町村で設置が進められている『こども家庭センター』です。
これまで、母子手帳の交付などを担う「母子保健」と、子育ての悩みや虐待対応を担う「児童福祉」の窓口は別々であることが多くありました。 この2つの専門的な機能を一つに統合し、妊娠の届出の時から、子育てに関するあらゆる悩みを一つの場所でワンストップで相談できるようにしたのが『こども家庭センター』です。
「こんな些細なことで…」とためらわないで。具体的なサポート内容
「赤ちゃんの夜泣きで寝不足…」「離乳食を食べてくれない」「夫が非協力的でイライラする」「近くに頼れる人がいなくて孤独…」。
『こども家庭センター』では、こうしたどんな些細な悩みにも、保健師や助産師、ソーシャルワーカーといった専門家が耳を傾けてくれます。 そして、家庭の状況に合わせて具体的な支援を組み合わせた「サポートプラン」を一緒に考えてくれるのです。
例えば、家事や育児のサポートが必要な方には「訪問家事支援」を、休息が必要な方には「ショートステイ」や「産後ケア」を紹介するなど、センターがハブとなって、子ども食堂や保育所、医療機関といった地域の様々なサービスにつなげてくれます。
一番大切なメッセージ「絶対に一人で抱え込まないで」
妊娠・出産・子育ては素晴らしい経験ですが、ホルモンバランスの大きな変化もあり、心も体も非常にデリケートで不安定になりやすい時期です。 不安や孤独を感じるのは、決して特別なことではありません。
「しっかりしなきゃ」と自分を追い詰めてしまう前に、お守りのように『こども家庭センター』という存在を覚えておいてください。お住まいの市区町村のホームページで検索したり、母子手帳をもらう時に場所を聞いたりして、ぜひ気軽に利用してほしい、と動画では強く呼びかけています。
もちろん、藤東クリニックでも妊娠中から産後のメンタルヘルスケアに力を入れています。妊婦健診は、赤ちゃんの成長だけでなく、お母さん自身の心と体の健康を確認する大切な機会です。どんな小さな不安でも、医師や助産師にいつでも気軽に話してください。