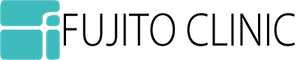藤東クリニックインサイト:「ライフステージで考えるこころの健康」総集編
広島県の産科婦人科「藤東クリニック」が運営するYouTubeチャンネル「藤東クリニックインサイト」では、女性の健康に関する様々な情報をデータに基づいて分かりやすく解説しています。今回は、シリーズ『ライフステージで考えるこころの健康』の総集編「健やかな社会を目指して」をご紹介します。
シリーズの概要
このシリーズでは、幼年期から老年期まで、各ライフステージにおけるストレス要因とその心身への影響について、令和6年版厚生労働白書のデータを基に詳しく解説しています。総集編では、これまでの内容を振り返りながら、「こころの健康」の重要性と、健やかな社会を目指すために私たち一人ひとりができることを考えています。
各ライフステージのストレス要因
幼年期・少年期・青年期
- 幼年期では養育者との安定した関係が情緒形成に不可欠
- 少年期では学校生活でのいじめや友人関係のトラブルが影響
- 青年期は仲間集団の役割が大きくなり、精神疾患のリスクが高まる時期
壮年期・中年期
- 仕事や家庭での責任増加による長時間労働やハラスメントがストレス要因
- 出産後の女性の約30~50%が「マタニティブルーズ」を経験
- 産後うつになる割合は母親で約10%、父親でも約11%
- 流産や死産など周産期喪失を経験した女性の約80%が「非常に辛かった」と感じる
- その辛さは1年経過後も約10%の方に残る
- 辛さを誰にも相談できないと感じる方が約30%存在
高齢期
- 退職や死別などの喪失体験が大きなストレス要因
- 「老老介護」の増加(要介護認定者数は約690万人)
- 介護者の約7割がストレスや悩みを抱えている
- 生活不活発病による機能低下やうつ症状のリスク
「こころの健康」を守るための具体的支援策
家庭での支援
- 家族間のコミュニケーションの充実
- 育児・家事の負担分担(共働き世帯が増加し、妻がパートタイム労働者の世帯は約200万から約700万世帯に増加)
- 男性の育児参加促進(育児休業取得率は女性約80%に対し男性は17%程度)
地域での支援
- 地域コミュニティへの積極的参加
- ひとり親世帯への支援(母子家庭約119.5万世帯、父子家庭約14.9万世帯)
- 地域の支援団体や相談窓口の活用
職場での支援
- メンタルヘルスケア制度の導入と相談窓口の設置
- 柔軟な働き方や休暇制度の整備(介護者の約6割は有業者)
- ワーク・エンゲイジメントを高めるための職場内コミュニケーション改善
支え合う社会づくりに向けて
個人レベルでできること
- 周囲の人への気遣いと声かけ
- 相談しやすい環境づくり
- 自分自身のストレスサインに気づく習慣
社会全体での取り組み
- 男性の育児参加を促進する環境整備
- 地域での介護支援サービスの充実
- 家族以外の支援者との連携強化
- メンタルヘルス教育の普及
- 多世代が関わる地域イベントの開催
視聴者へのメッセージ
藤東クリニックからのメッセージとして、「こころの健康」を守るためには以下の点が重要だと伝えています:
- 自分自身を大切にし、ストレスを一人で抱え込まない
- 不安や悩みを感じたら、専門家や信頼できる人に相談する勇気を持つ
- 周囲の人への気遣いを忘れず、相談しやすい環境をつくる
- 地域や職場での支え合いの仕組みづくりに参加する
この動画は、各ライフステージで直面する可能性のあるストレスについて理解を深め、それに対する適切な支援方法を知ることで、視聴者一人ひとりが健やかな社会づくりに貢献できることを伝えています。小さな気遣いや行動から始めることで、大きな変化につながることを強調しています。
藤東クリニックインサイトのYouTubeチャンネルでは、この他にも女性の健康に関する様々なテーマを取り上げていますので、ぜひチェックしてみてください。