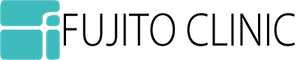動画の概要
藤東クリニックのYouTubeチャンネル「藤東クリニックインサイト」では、シリーズ『ライフステージで考えるこころの健康』の一環として「高齢期・老年期:喪失体験と孤独への対処法」をテーマにした動画を公開しています。この動画では、65歳以上の高齢期・老年期における喪失体験や孤独感について、令和6年版厚生労働白書などの信頼性の高いデータを基に詳しく解説しています。
高齢期・老年期の特徴
高齢期・老年期(65歳以上)は人生の完成期とも言われ、豊かな収穫を得られる時期である一方、様々な喪失体験に直面する時期でもあります。日本の総人口に占める65歳以上の割合は29.3%(約3,625万人)と過去最高を更新しており、75歳以上の方も2,076万人(総人口の16.8%)に達しています。
高齢期における喪失体験と影響
高齢期には以下のような喪失体験が増加します:
- 退職による社会的役割の喪失
- 配偶者や友人との死別
- 住み慣れた家から施設への転居
- 病気や障害による機能低下
これらの喪失体験は、孤独感や生活の不活発さを引き起こし、こころの健康に大きな影響を与えます。要介護認定を受けている方は約690万人で、2000年と比較すると約2.7倍に増加しています。また、「老老介護」の割合も約8割近くに達しています。
高齢期の孤独・孤立の実態
高齢期の孤独・孤立は深刻な問題となっています:
- 65歳以上の一人暮らし世帯は約683万世帯
- 高齢者で孤独・孤立を感じている方は約30%以上(約1,092万人)
- 60歳以上で「2~3日に1回以下」しか人と話さない方は男性で約2人に1人、女性で約3人に1人
- 「1週間に1回以下」しか話さない方も男性で5人に1人、女性で7人に1人
このようなコミュニケーション不足は生きがいの喪失や不安感を引き起こし、「生きがいを感じていない」と回答した高齢者は全体で12.9%ですが、「近所付き合いがほとんどない」方では39.0%、「困った時に頼れる人がいない」方では55.8%にも上ります。
さらに、65歳以上の高齢者による孤独死数は2003年の1,441人から2018年には3,867人と、15年間で約2.6倍に増加しています。
対処法と予防策
高齢者ご自身ができること
- 社会参加: 趣味やボランティア活動などの社会参加をしている高齢者は、抑うつ症状を感じる割合が約半分に減少
- 運動習慣: 週に1回以上外出する高齢者は、外出しない人より認知症発症リスクが約30%低下
- 健康管理: 定期的な健康診断を受けている高齢者は、生活満足度が約20%高い
- 相談窓口の活用: 地域包括支援センターや医療機関など専門家への相談
周囲の方々ができること
- 傾聴と共感: 「話をじっくり聞いてくれる人がいる」と感じている高齢者は、生きがいや安心感を感じる割合が約70%以上
- 見守り: 変化に早期に気づき、適切なサポートにつなげる
- 専門機関への相談: 地域包括支援センターなど専門機関の活用
社会全体での取り組み
家庭での取り組み
- 家族間での日頃からのコミュニケーション
- 要介護者等の主な介護者は「同居している家族」が54.4%(配偶者23.8%、子ども20.7%)
地域社会での取り組み
- 地域包括支援センターや高齢者サロンの活用
- ボランティア活動や趣味教室への参加は、孤独感や抑うつ症状を約30%以上軽減
職場での取り組み
- 高齢期に入っても働き続けられる環境づくり
- 65歳以上の雇用率は25.2%と過去最高
- 世代間交流の促進
まとめ
高齢期は誰にでも訪れる人生の大切なステージです。喪失体験や孤独を前向きに捉え、ご本人だけでなく家族や地域社会全体で支え合う意識を持つことが重要です。一人ひとりが身近なところからできることを始めていくことで、高齢期を安心して迎えることにつながります。
次回は、シリーズの総まとめとして『シリーズ総集編:健やかな社会を目指して』をお届けする予定です。