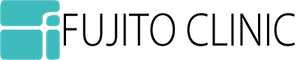周産期喪失とは
周産期喪失とは、妊娠中や出産直後に赤ちゃんを亡くす経験のことを指します。具体的には流産、死産、早期新生児死亡などが含まれます。これは決して珍しいことではなく、自然流産は全妊娠の約10~15%に起こるとされており、女性の年齢が高くなるほど発生率が高くなります。厚生労働省の「人口動態統計」によると、2022年には妊娠12週以後の死児の出産数が1万5,179胎にのぼっています。
周産期喪失の心理的影響
周産期喪失を経験すると、多くの方が深い悲しみや喪失感を感じます。「何か自分に原因があったのではないか」という罪悪感や、「何もできなかった」という無力感に苦しむこともあります。
厚生労働省の調査によると、流産または死産を経験した直後は約80%の方が「非常に辛かった」と回答しています。この辛さは時間の経過とともに徐々に和らいでいきますが、1年以上経っても約10%の方が「非常に辛かった」と回答しており、長期間にわたって強い悲しみを感じ続ける方がいることがわかります。
相談状況と回復のためのサポート
流産や死産が分かった直後に感じた辛さについて、誰かに相談した人は61.6%、相談していなかった人は30.3%でした。相談しなかった理由としては、「相談しても変化が期待できない(仕方がない)と思った」が41.5%、「流産や死産について、人に話すことに抵抗があった」が39.3%と心理的な理由が多く見られました。
周産期喪失からの回復には、悲嘆からの回復は人それぞれであり、時間を要することを理解することが大切です。無理に早く立ち直ろうとする必要はありません。また、一人で抱え込まずに、信頼できる人に話を聞いてもらうことも重要です。こども家庭庁では、流産・死産等を経験された方向けの相談窓口を開設していますので、必要な時には活用することをお勧めします。
子育ての喜びと負担
子育ては人生における大切なライフイベントであり、多くの喜びをもたらします。文部科学省の調査によると、0~18歳の子どもを持つ親に「子育てをしていて良かったと感じる時」を尋ねたところ、「子どもが喜んだ顔を見るとき」が74.3%で最も高く、「子どもの成長を感じるとき」が67.5%、「子どもと話したり、遊ぶとき」が25.6%となっています。
一方で、子育てをめぐる社会環境は大きく変化しています。1985年以降、男性雇用者と無業の妻からなる世帯数は減少傾向にある一方、共働き世帯は増加しています。特に妻がパートタイム労働者の世帯は、約200万世帯から約700万世帯へと大幅に増加しています。
育児休業と育児時間の現状
育児休業取得率を見ると、女性は過去10年以上にわたり80%台で推移している一方、男性は2022年度実績でも17.13%と低水準です。ただ、男性の育児休業取得率は近年上昇傾向にあります。
総務省の「社会生活基本調査」によると、共働き世帯(6歳未満の子どもを持つ夫婦と子どもの世帯)の育児時間は、夫婦ともに経年的に増加していますが、2021年においては、妻が3時間24分に対し、夫が1時間3分と、依然として大きな差があります。
ひとり親家庭の状況
日本には、母子家庭が119.5万世帯、父子家庭が14.9万世帯と多くのひとり親家庭が存在しています。ひとり親家庭の親は、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担うため、様々な困難に直面することがあります。
厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、子どもについての悩みを抱えているひとり親は、母親では母子世帯の約7割、父親では父子世帯の約6割にのぼっています。悩みの主な内訳では、「教育・進学」が最も多く、母親では60.3%、父親では57.5%を占めています。
母子世帯と父子世帯の世帯年収は児童のいる世帯全体の平均年収よりも低く、母子家庭の平均年間収入は373万円で、児童のいる世帯の平均所得を100とすると45.9、父子家庭は606万円で74.5となっています。
社会全体での支え合い
子育て支援の充実は社会全体で取り組むべき課題です。職場における育児休業制度や短時間勤務制度の活用促進、地域社会における子育て支援センターやファミリーサポートセンターの活用、家族や友人など身近な人のサポートなど、様々な面からの支援が重要です。
特に、育児時間の男女差を減らし、夫婦で協力して子育てを行うことが、母親の抑うつ・不安の軽減につながります。また、子育てに関する悩みを一人で抱え込まず、相談できる環境づくりも重要です。
「子育ては社会全体で行うもの」という意識を持ち、互いに支え合う社会を目指していくことが大切です。藤東クリニックでは、皆さんの健康と幸せをサポートしています。皆さんが笑顔で過ごせる日々を心から願っています。