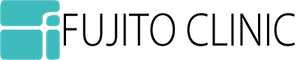【女性とこどものSOS】DV・虐待・薬物問題…その根底にある「孤独」と、私たちにできること
いつでも誰とでも繋がれるスマートフォン。便利な情報を得る一方で、SNSなどで他人と自分を比べて落ち込んだり、漠然とした疲れを感じたりした経験はありませんか?
当院のYouTubeチャンネル「藤東クリニックインサイト」では、動画シリーズ『現代女性のこころの健康を守るために知っておきたいこと』を配信しています。今回はその第4回「【女性とこどものSOS】DV・虐待・薬物問題…知っておきたい現状と私たちにできること」の内容を、データと共に詳しくご紹介します。
一見すると無関係に思えるDV・虐待・薬物といった問題は、実は「孤独」や「生きづらさ」という共通の根っこで繋がっています。決して他人事ではないこの問題について、一緒に考えていきましょう。
「繋がっているのに孤独」という現代の感覚
総務省の調査によれば、スマートフォンの世帯保有率は9割を超え、SNSの利用も全世代で増加しています。しかし皮肉なことに、こうしたデジタルの繋がりは、逆に人々の孤独感を深めているという側面も指摘されています。
内閣官房の調査では、若い世代ほど孤独を感じる傾向にあり、特に20代女性の8.7%、30代女性の9.0%が「しばしば、または常に孤独を感じる」と回答しています。これは、およそ10人に1人が強い孤独を感じながら生活している計算になります。
こうした「生きづらさ」や「孤立」が、より深刻な問題の土壌になっている可能性があるのです。
高止まりするDV相談件数と、こころに残る傷
配偶者やパートナーからの暴力、いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)の相談件数は、決して減少していません。全国の配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、2020年度に過去最多を記録した後も、2022年度で12万件を超える高い水準で推移しています。これはあくまで相談に至ったケースであり、「氷山の一角」に過ぎないと言われています。
暴力がもたらす影響は、身体的なものだけではありません。被害経験者の60.0%が生活上の変化を実感しており、その中で最も多かった回答は「自分に自信がなくなった」(26.2%)でした。次いで「夜、眠れなくなった」(20.8%)、「心身に不調をきたした」(18.2%)と続き、深くこころが傷つけられている実態がうかがえます。
過去最多を更新し続ける児童虐待
暴力のある家庭環境は、子どもに深刻な影響を及ぼします。児童相談所が対応した虐待の相談件数は、2022年度には21万9,170件と過去最多を更新。この10年間で約3.3倍にも増加しています。
虐待の種類で最も多いのは、暴言や無視、子どもの目の前で家族に暴力をふるう(面前DV)といった「心理的虐待」で、全体の約6割(59.1%)を占めています。夫婦喧嘩を子どもに見せることも、子どもの心を深く傷つける虐待であるという認識が、今、社会全体で求められています。
若者に忍び寄る薬物の罠 ― 大麻とオーバードーズの急増
孤立や生きづらさは、若者の薬物問題にも繋がっています。特に深刻なのが大麻です。大麻事犯の検挙者数は、この10年で30歳未満では5.4倍、20歳未満では15.0倍と驚異的な増加を見せています。
その背景にはSNSの存在があります。30歳未満の検挙者が入手先を知ったきっかけの3分の1以上が「インターネット経由」で、そのうちの約9割がSNSを利用していました。「危険ではない」「海外では合法」といった誤った情報が、薬物へのハードルを下げてしまっているのです。
さらに深刻なのが、市販の風邪薬などを大量に摂取する「オーバードーズ」です。2022年には、薬物依存の治療で精神科を受診した10代患者の3人に2人(65.2%)が、主たる薬物が市販薬でした。2014年にはこの割合が0%だったことを考えると、その急増ぶりは異常事態と言えます。ある調査では、高校生の約60人に1人が過去1年以内に市販薬の乱用経験があると推計されており、これは違法薬物である大麻の10倍にあたる数字です。
孤独は誰の身にも起こりうる。社会で取り除くべき「壁」とは
なぜ、人はこれほどまでに孤立してしまうのでしょうか。孤独は本人の性格だけの問題ではありません。
孤独を感じている人は、そうでない人に比べて、「家族との死別」や「一人暮らし」、「心身の重大なトラブル」といった、つらい出来事を経験した割合が著しく高いというデータがあります。つまり、孤独は誰の身にも起こりうるのです。
車いすの方が階段を上れないのは、本人のせいではなく「そこにエレベーターがない」という社会の問題です。同じように、こころの不調で苦しむ人を「本人の弱さ」で片付けるのではなく、気軽に相談できない、助けを求めにくいといった社会の側の「壁(社会的障壁)」を取り払っていく必要があります。
あなたは一人じゃない。どんなことでも相談してください。
もしあなたの周りに悩んでいる人がいたら、まずは話を聞き、専門の窓口に繋ぐ手助けをすることが大切です。
そして、ライフステージの変化も多い女性は、男性よりも気分の落ち込みや不安を感じやすいという調査結果もあります。どうか一人で抱え込まないでください。
私たち産婦人科医は、女性の生涯に寄り添い、皆さんの心と体の健康を支えるパートナーです。「こんなことを相談していいのかな…」などと、ためらう必要は全くありません。どんな些細な不安でも、私たちを頼ってください。あなたは、決してひとりではありません。